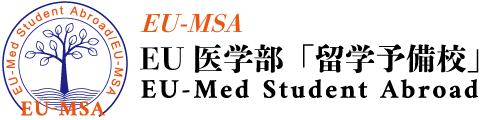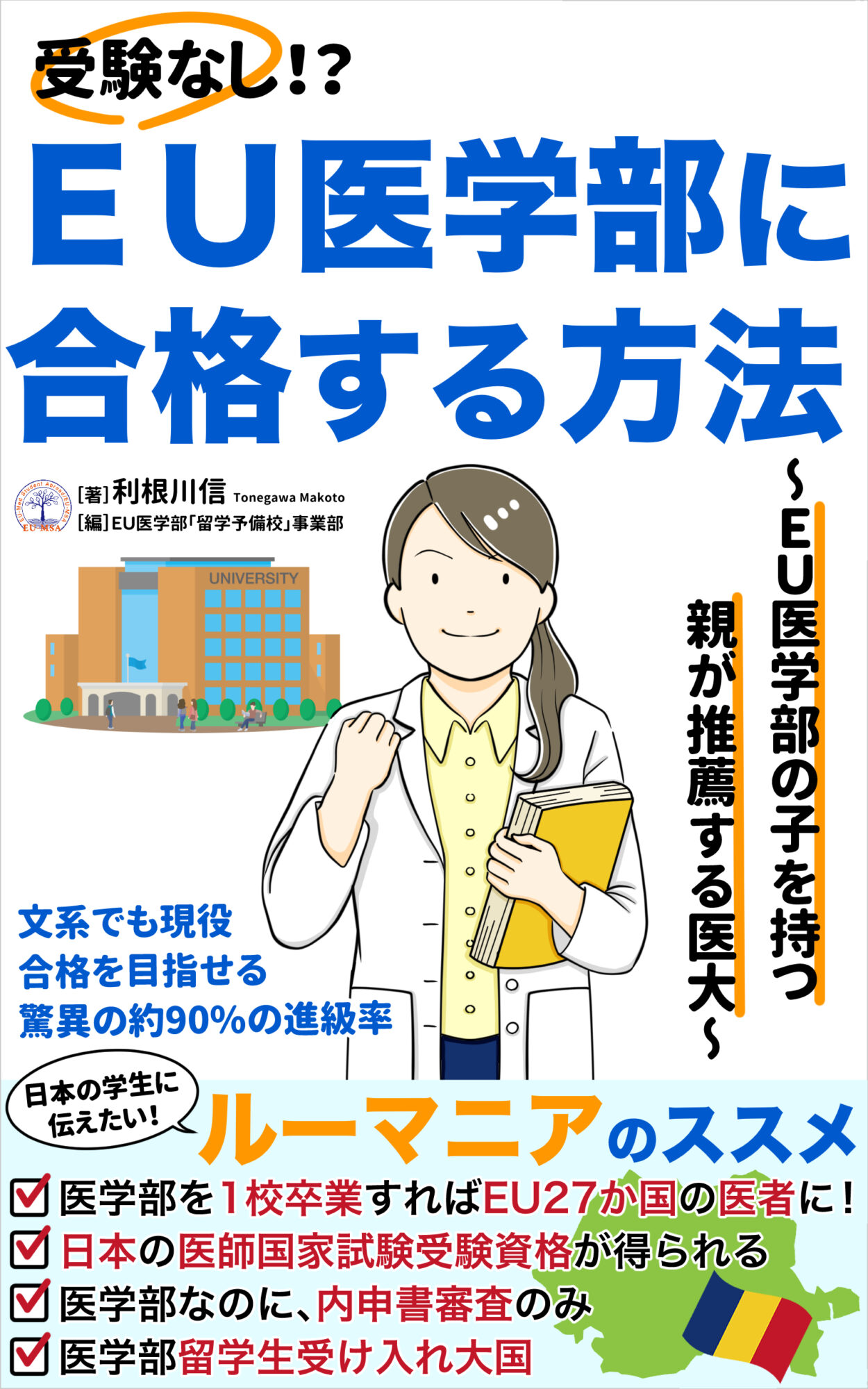10.【EU医学部留学】世界で初めて「麻酔手術」をしたのは日本人だった

嘉永六年六月(西暦1853年七月)浦賀に来航したアメリカ合衆国のペリー提督は「日本人は極めて勤勉で『器用』な人民」で(略)、「強力な競争者として、将来の機械工業の成功を目指す競争に加わるだろう。」(『ペリー提督日本遠征記』)と評している。
「器用」といえば、江戸中期、室町時代の管領畠山家ゆかりの医師の東洞嫡男南涯に学んだ弟子 華岡青洲(はなおかせいしゅう)が母親と妻で臨床治験をしてまで、世界で初めて全身麻酔による乳癌の外科手術を成功させた。
当時の華岡青洲の努力は現在の倫理感においては、普通ではなかった。
実母の於継と妻の妹背加恵が実験台になることを申し出て、数回にわたる人体実験の末、於継の死、加恵の失明という大きな犠牲の上に、全身麻酔薬「通仙散」(別名 麻沸散まふつさん)を完成させたとされている。
欧米で初めて麻酔手術が行われたのは、1846年(USA)ウィリアム・T・G・モートンによるジエチルエーテルを用いた麻酔の手術です。華岡青洲の手術よりも40年以上も後のことであった。
華岡青洲はまさに「世界に通じる優れた外科医」だったことがうかがえる。日本も世界も戦争が起こるたびに外科医たちが活躍し、腕を磨いた歴史がある。しかし、江戸時代の戦争の無い武家の時代であってもそのような世界に通じる「医道」を極めた医者たちがいたのである。
昭和27年(1952年)、「外科を通じて世界人類に貢献した医師のひとり」として、USAのシカゴにある国際外科学会付属の栄誉館に祀られた。
詳細はAmazon Bookをご購入の上、お読みください
「EU医学部に合格する方法」
EU医学部に子がいる親が推薦する医大 (医学部留学)
オンデマンド (ペーパーバック) – 2025/2/17 利根川信 (著)