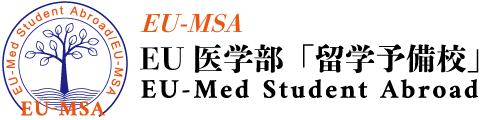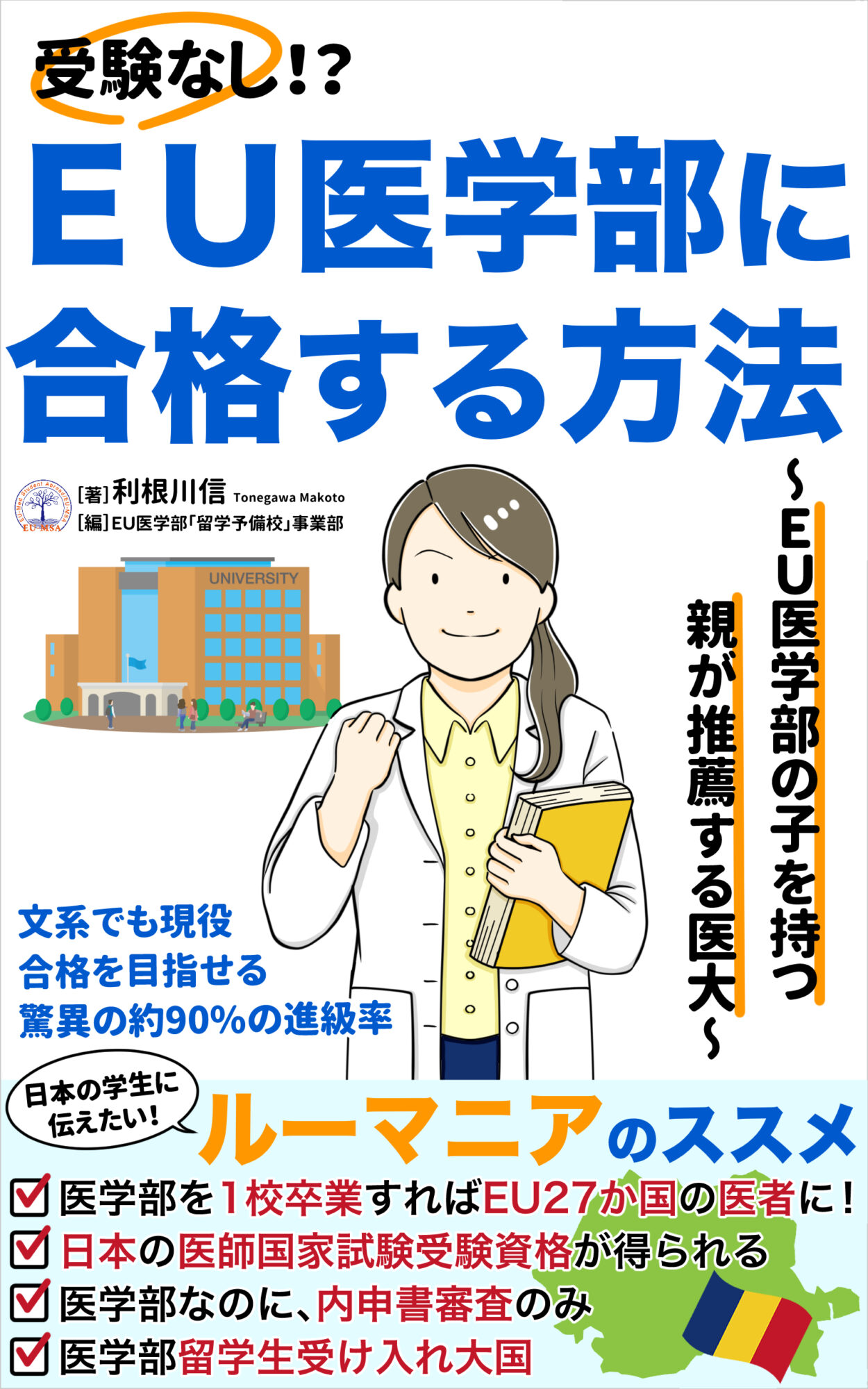9. 【EU医学部留学】1474年日本独自の鍼灸が海を渡る 記事

室町時代の話である。
三代目能登守護畠山義統は、足利将軍家一門の「家格」でありながら、「応仁の乱」では西軍に属して、中央政府(東軍側幕府)に対抗していた。「独立独歩」的に活動をしていた義統は、文明五年(1473年)九月に中央政府にはなにもいわず、独断で「畠山義統使節団」を李朝鮮国へ派遣をした。
この中央政府への「挑戦」的行為が思いがけなく、義統を「ヒーロー」にしてしまった。
畠山義統は使節団副官として信濃国の医僧の良心(秦久秋の子)を指名し、次の二つの鍼灸書を李朝鮮国へ献上させた。(「医道」『神応経』)
①日本独自の鍼灸(しんきゅう)療法『八穴灸法』(註 医学用語)と、
②応永三二年(1425年)に中国明国で序刊(初版)された鍼灸書『神応経』である。
偶然だが、当時李朝鮮国では、たまたま「鍼灸」の専門医を教育している時期で、畠山義統が献上した鍼灸療法『八穴灸法』と『神応経』が研究され、李朝鮮国の医療発展へ大いに貢献したという。
そして、早くも翌年文明六年(1474年)には日本の『八穴灸法』を加えた鍼灸書『神応経』改訂復刻版が李朝鮮政府により木版印刷された。(印刷なので、広く広まり、中国にも送られていたものと思われる。)
さらに、それが江戸時代の正保二年(1645年)に日本で再復刻され、江戸時代の医学に貢献をした。またさらに、それが、近年平成二年(1990年)には江戸の再復刻版に基づく活字本が北京の中医古籍出版社から再々復刻され、この中国再々復刻版は日本・韓国にも輸出されている。
もともと「応仁の乱」の東西両将軍(東軍は管領細川勝元、西軍は老将山名宗全)が同年文明五年(1473年)に急死し、平和交渉が頓挫(とんざ)していた「戦争の空白」の隙(すき)を狙って勝手に「畠山義統使節団」を李朝鮮へ送ったものであり、西軍武将として中央政府(東軍)への「挑戦」的行為だったが、そんな義統の個人的な思いを遥かに超えて、鍼灸書『神応経』は明版(初版)ー>畠山義統の秘伝献上ー> 李朝版ー> 江戸版ー>北京版ー> 日本・韓国翻訳版と約550年にわたり少なくとも3国間の伝承をたどり現代にいたっている(「日中韓」)。
「応仁の乱」を通じて中央政府に「挑戦」をしていた畠山義統ではあったが、日本国内では本人が知らない内に、中央からの支配を嫌う「地方の武士のヒーロー」(「七つ尾36号」)になり、海外では、時代を超え、国を超えた「世界鍼灸医療のヒーロー」となった。さらに、韓国・中国から一方的に医術をうけ入れていた時代に、日本が海外へ逆に影響を与えた数少ない一例をつくった「日本の東洋医学史のヒーロー」となった。
能登守護として、政治・軍事に加え先祖代々の「金創外科医術」「鍼灸医学」の知識・能力を備えた教養人畠山義統の晩年は「中風」を患っていた模様で(「八坂神社」)、明応六年(1497年)八月に没した。推定五五歳。法名は大寧寺殿大彦孫公大禅定門(「永光寺年代記」)
詳細はAmazon Bookをご購入の上、お読みください
「EU医学部に合格する方法」
EU医学部に子がいる親が推薦する医大 (医学部留学)
オンデマンド (ペーパーバック) – 2025/2/17 利根川信 (著)